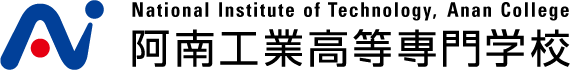リサーチユニット
リサーチユニットとは
令和3年10月より、研究の質保証、地域連携と研究活動活性化による特例認定専攻科の持続的発展を目指した「外部研究メンター導入による研究活動を活性化させる共創的リサーチユニット制度」を開始しました。
本制度の目的は、以下の4点となります。
・教員が継続的に専門分野のフルペーパーを書ける研究活動ができる
・専攻科生が質の高い学術レベルを獲得できる
・阿南高専科学技術振興会(AST)や外部の研究コミュニティーとの連携が深まり、地域貢献や研究の質を向上できる
・科学研究費補助金やJST等の外部予算をコンスタントに獲得できる
本制度は、リサーチユニット長がリサーチユニット長、専攻科長、地域連携・テクノセンター長及び副校長を構成員とする校長直属のリサーチユニット推進コミッティーの中心となり、社会からの要請に応える研究や将来を嘱望される萌芽的な研究を推進するとともに、リサーチユニットのゲートキーパーとなり、各ユニットの希望や悩みを聞き取りながら研究活動を支援する制度です。リサーチユニットの形成を志願する本校教員が外部有識者による外部メンターの支援を受けながらactiveに運営することに特徴を持ちます。外部メンターは、リサーチユニットをメンタリングして教員の研究活動をサポートするとともに、リサーチユニット長が各リサーチユニットの外部メンターからの活動評価を評価し、各リサーチユニットに必要な支援等を校長に提案することになります。
また、ユニット教員のモチベーションや時間を確保するために,研究活動で自由に使えるディベートルーム「Research Commons」、研究に係る出張・実験や論文作成における時間を与える「ショートサバチカル」、高専のOB・OGを招いた「研究促進合宿」等の施設設備の充実や活動支援策も整備しています。